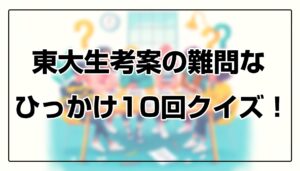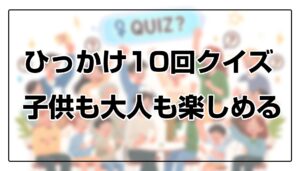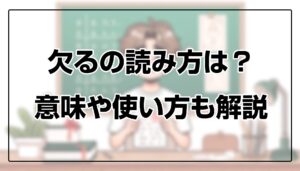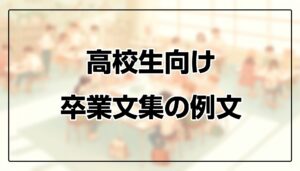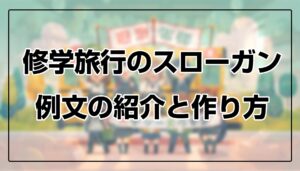「肌色」という表現を耳にする機会は減ったように感じますが、あなたはこの言葉をまだ使用していますか?
以前、私が小さい頃によく使ったクレヨンにも「肌色」という名前がついていましたが、今は「うすだいだい」という色で表されていました。
同じ色の認識が共有されていれば、その用語を使うことに対して特に不都合は感じません。
とはいえ、日本は多種多様な肌の色を持つ人々が増えており、国籍に関係なく「肌色」と一括りにするのは適切ではないかもしれません。
この記事では、代わりに使用できる「肌色」という言葉の他の選択肢や、その変化に至った背景について詳しく解説していきます。
肌色が言い換えられた3つと色の意味を紹介
うすだいだい
最初に紹介するのは「うすだいだい(薄橙)」という色です。
この色は、ダイダイオレンジという果物から名付けられており、色味はダイダイよりも薄く抑えられたオレンジ色を指します。
ダイダイオレンジの色合いは、生き生きとしたオレンジ色で、非常に目を引きます。
オレンジ色と同義で、煌びやかな黄色と赤の中間色に位置します。
ペールオレンジ
次に挙げるのは「ペールオレンジ」という色です。
ペールオレンジは、英語のpaleが「薄い」という意味を持ち、オレンジ色の明るいバリエーションを示します。
簡単に言えば、うすだいだいとペールオレンジは色合いがほぼ同じと言えます。
ベージュ
肌色のもう一つの代替語として「ベージュ」があります。
ベージュはもともとフランス語に由来する色名で、淡くて明るい黄色や茶色のニュアンスを持ちます。
日本工業規格では、淡い灰色の赤みがかった黄色と定義されています。
日常的な会話では、うすだいだいやペールオレンジといった表現はあまり耳にしませんが、化粧品においてはライトベージュやピンクベージュといった色が見られます。
ベージュは日常生活でよく見かける色であり、肌色の新しい表現としてなじみやすく、違和感なく使えます。
「肌色」の言い換えはいつ頃からなの?
「肌色」とは、もともとは日本人特有の肌の色合いを指す、淡いオレンジ色系の色名でした。
この言葉は、仏教が民衆に広がる前の日本、江戸時代以前には「宍色(ししいろ)」として知られていました。
「宍(しし)」は古くから食べられる動物の肉を示す言葉でしたが、徳川綱吉の「生類憐れみの令」以降、「宍色」の呼び名は避けられ、「肌色」という言葉が一般的になったとされています。
自由画教育の導入された大正時代に入ると、絵具や色鉛筆の需要が増えました。
特に昭和の初期には、子供たちが人の顔を描く際に使う色として「肌色」が一般的に使われるようになりました。
しかし、その後この用語は徐々に使われなくなりました。
その転換点となったのは、1950年代から60年代にかけての「アフリカ系アメリカ人公民権運動」の波及でした。
この運動の影響を受け、人の肌色を指す際に使われていた英語の「flesh」という単語も、その後「peach」という表現に変わりました。
これは、肌色を一つの色に限定することの適切さに疑問が投げかけられた結果です。
「はだ色」という表現が変わった背景はなんなの?
残念ながら、日本においては人種差別に対する認識が低いと長らく指摘されてきました。
そんな状況の中、消費者の中には、多民族国家である日本で単一の色を「はだ色」とすることに差別的な意味合いがあると指摘する声が上がりました。
学校教育の現場からも、「はだ色」という表現を使うことに対する抵抗感が強まり、この問題は2000年頃、大きなクレヨンメーカーが製品名を変更する契機となりました。
ぺんてるは「ペールオレンジ」へ、サクラは「うすだいだい」という名称へと切り替えました。
これにより、色鉛筆や絵の具などの画材からも「はだ色」という名前が次第に姿を消していったのです。
まとめ
「はだ色」の色名の変更は、商品ラベルにおける色の表記を更新することから進みました。
それにもかかわらず、日本においては肌の多様性や人種に関する認識がまだ十分ではないとされています。
「肌色」という表現は、状況に応じて適宜使用可能ですが、肌の色が一様ではないという現実を正しく理解し、尊重することが大切です。